ご相談はこちら
人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
先日、知り合いの会社で悪質な退職をした社員がいました。
管理していた共有サーバー内の重要データをすべて削除して辞めてしまい、引継ぎも一切なく、会社への強い不満を抱えていたようです。このような悪質な退職に対して、会社は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
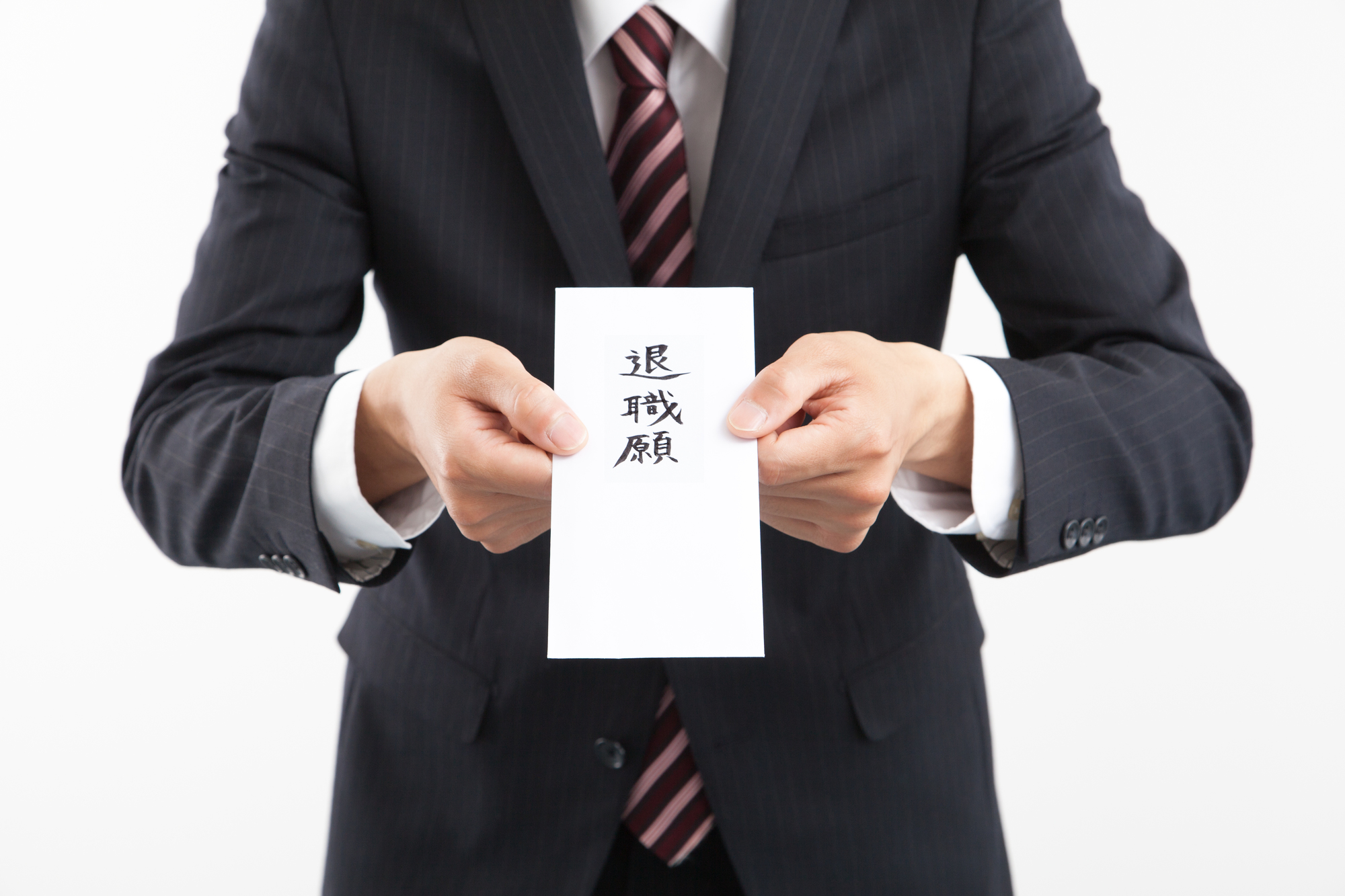 会社への恨みを晴らすかのような「リベンジ退職」は、単なるモラルの問題ではなく、会社の事業継続を脅かす重大な違法行為です。
会社への恨みを晴らすかのような「リベンジ退職」は、単なるモラルの問題ではなく、会社の事業継続を脅かす重大な違法行為です。
特に、業務データを意図的に削除する行為は、明確な犯罪行為に該当する可能性があり、会社は毅然とした法的措置を取ることが可能です。
このような行為は、刑法上の「電子計算機損壊等業務妨害罪」にあたるほか、民法上の「不法行為」として、会社が被った損害の賠償を請求することができます。
----------------
【判例紹介】「バルス!」と名付けたプログラムで会社のデータを消去した元従業員
----------------
退職時に会社のデータを削除した元従業員に対し、裁判所が損害賠償を命じた判例があります(徳島地裁 令和5年(ワ)第38号)。
この事件では、退職する元従業員が、自身の最終出社日の約1ヶ月後の退職日に、自動で起動するデータ削除プログラムを会社の共有PCに設定。
退職日当日、プログラムが作動し、自身が開発したソフトウェアや実験データなど、232個のフォルダ内のファイルが消去されました。また、この削除プログラムには、某アニメ映画の「滅びの呪文」として知られる「バルス」という名前が付けられており、ネット上でも話題になりました。
会社側は、データの再開発費用や元従業員に支払った給与総額など、約2,581万円の損害賠償を請求。これに対し、元従業員側は「ライセンス違反のソフトだったので会社のために削除した」「バックアップを取らない会社にも過失がある」などと反論しましたが、裁判所はこれらの主張を退け、元従業員の行為を悪質な不法行為と認定。
データの再開発費用や代替品の購入費用などを損害として認め、元従業員とその身元保証人に対し、連帯して約577万円の損害賠償を支払うよう命じました。
----------------
会社が取るべき具体的な対応ステップ
----------------
万が一、同様の事態が発生した場合、会社は以下の手順で冷静に対応してください。
(1)証拠の保全【最優先】
PCのアクセスログやサーバーの操作履歴など、デジタル・フォレンジック(デジタル鑑識)の専門業者に依頼してでも、客観的な証拠を確保します。これが法的措置の生命線です。
(2)データの復旧
バックアップからの復旧を試みます。復旧にかかった費用は、損害賠償額に含めることができます。
(3)専門家への相談
証拠を持って速やかに弁護士に相談し、損害賠償請求や刑事告訴の準備を進めます。
(4)警察への被害届提出
悪質性が高い場合は、ためらわずに警察へ被害届を提出しましょう。刑事事件として立件されれば、相手に与えるプレッシャーは絶大です。
-----------------
最強の対策は「予防」にあり
----------------
リベンジ退職は、一度起きてしまうと甚大な被害をもたらします。最も重要なのは、このような行為が「できない」「割に合わない」と思わせる仕組みを平時から構築しておくことです。
【アクセス権限の厳格化】
従業員の役職や職務に応じて、データへのアクセス・操作権限を必要最小限に設定します。特に退職予定者については、最終出社日をもって速やかに権限を停止するルールを徹底しましょう。
【バックアップ体制の強化】
重要なデータは、必ず自動でバックアップが取られる仕組みを構築し、その保管期間も十分に確保します。
【誓約書の徹底】
入社時・退職時に、情報管理に関する誓約書(データの私的利用・破壊の禁止、退職時の情報返却・破棄義務など)に署名させ、違反した場合の罰則についても明記しておきます。
リベンジ退職は、社員個人の問題であると同時に、会社の情報管理体制の脆弱性や、従業員の不満を放置した組織マネジメントの問題でもあります。日頃から従業員との対話を密にし、不満の芽を早期に摘み取ることが、最も根本的なリスク管理と言えるでしょう。